さとうが生きている21世紀の方が24世紀より未来っぽい感覚になっちゃうような話。
半世紀以上もむかしに書かれた話だから、緊迫しながらもちょっとのほほんとした味わいがある。
でも、ちゃんとオチはつくよ。
【分解された男】のあらすじ
24世紀、超感覚者による警察本部精神刑事部の活躍で犯罪を計画することさえ困難な時代。
一大産業王国を築こうとするベン・ライクがライバルを倒すために殺人行為に及ぶ。
超感覚第一級の刑事部長パウエルは、ベンがどうやって殺人を計画し実行したのかを解明しなければならない。
ライクと超感覚者の攻防や、いかに!
ベンは顔のない男の悪夢に悩まされるのよ。そこがポイント。
古き、良心的時代の話だと思ってね
はじめに言っとく。
この話は1951年から「ギャラクシー・サイエンス・フィクション」というアメリカのSF雑誌に連載されて、1953年に単行本として発表された。(ちなみに本邦初版は1965年)
だから、文章とか表現とか、まあ古い。
ストーリーも殺人事件をめぐるアレコレなんだけど、まあ、のほほんとしてる感がある。
そしてもちろん、どんな時代のどんな特性の人間にも良い人と悪い人がいるのは当然なんだけど、令和の時代に生きていると、まあ良心的な感じを受ける。
 さとう
さとうなんていうか、21世紀より古い24世紀、なんちゃって
だからSF小説なんだけど、チャップリンの映画を見ているような感じだ。
翻訳も古くて、ちょっと読みづらい。
そして古いってことは、お決まりのことだけど、男女差別につながるような表現が出てくるってこと。
1951~1953年に書かれているからしかたがないんだけど、やれやれって感じだ。
第1回ヒューゴー賞を受賞してる作品です
前にもSF小説の賞についてチラッと触れたけど、ヒューゴー賞は現存する中で最も歴史の古いSF・ファンタジー文学賞。
いわゆるSF作品しか受賞しないわけではなくて(そもそもSFはジャンルの正確な定義について普遍的な合意がなされてないので)ファンタジーやホラーが受賞してたりもする。
ヒューゴー賞の公式サイトでは「ヒューゴー賞にふさわしい作品とは、投票者たちがヒューゴー賞を贈ることによって示される」というふうに説明されてた。



公式サイトは英語なので、さとうはwikipediaから知ったけど
だからさとうとしては、本屋大賞みたいなものだなって考えてる。
まったくの素人が選ぶわけではなくて、世界SF協会の会員が「これがいいんじゃない?」って選ぶからね。
でも世界SF協会って、ワールドコン(世界SF大会)を運営する「非営利のファン団体」って感じなのよ。
「ワールドコンに参加しまーす」って参加費を払った人が協会員になれるってわけなの。
賞自体は1953年のワールドコンにて、アカデミー賞をヒントに提案されたらしい。
実際には作家だとか翻訳者だとか編集者だとか科学者だとか、物販ディーラー、アーティスト、広告業者なんかもお金を払って参加する。
だから素人ばかりじゃないってわけ。
でも、ほら、非営利だから、金の力で受賞とかはないので、読んでみようかなってすなおに思える。
で、栄えある第1回受賞作が、この「分解された男」
でも、この作家、アルフレッド・ベスターはどっちかっていうと「虎よ、虎よ!」の方が有名な気がする。
第1回受賞でも、人の記憶に長く残るのはなかなかむつかしいのかな。
「虎よ、虎よ!」もついでに紹介しておく。
先出は後出に影響をおよぼす
さとうの持っている本は20年も前のもので、日本語の誤植もある。
翻訳されている表現も古くて、若い人には読みにくいだろうからムリに読んでとは言わない。
でも、新しい作品に触れたときに「アレ?これってどこかで似たような話があったな」みたいな記憶が妄想をひもづけてくれて、さとうは楽しくなっちゃう。
たとえば。
トム・クルーズの「マイノリティ・レポート」なんかも、プリコグと呼ばれる予知能力者が未来の殺人を予知することで犯罪が90%減少していたっていう設定で話が進む(もっとも原作はフィリップ・K・ディック)
あー、超能力者ってむかしからこういう役割を振られるよね、とか納得する。
あるいは、自分には超能力があると疑わず、採用してほしいと思う大勢の一般人が超感覚連合会館の受付に押しかける。
で、も。
精神波で呼びかけられた「これが聞こえる人は、左手の従業員専用と書いた入口からはいってください」が聞こえた人だけが、従業員専用のドアに向かう。この青年は精神波の呼びかけに気がついた、つまり隠れたエスパーだったというシーン。
これ、「メン・イン・ブラック」っていう映画のシリーズのどこかで見なかったかな?
なんにしろ、先に表に出たものは、後から出てくるものに影響をおよぼす。
SFって、科学の発展とともに、そういう影響に鍛えられて世界を広げてきたんだね。
まあ、フィクションってどんな分野もそういうものだけど。
さとうがこの本を読んだ理由
さとうは、賞を取ったものが自分の好みに合うとは限らないって考えるので、そうそう、受賞作を読もうってならない。
でもこれは、ヒューゴー賞の第1回受賞作、っていうところに興味があった。
半世紀以上もまえの、第1回受賞作ぐらいなら、読んでみてもいいんじゃないって思った。
なぜならヒューゴー賞の作品って、やっぱりおもしろいものがある。
だから「第1回受賞作ってどんななの?」って思うじゃないの。
思うに、よほどむかしに翻訳されている作品は、もういちど新訳を出したらいい。
読みやすくなったり理解しやすくなったり(だって作中のギャグが古すぎて若い人には全然わからないものになってる)すれば、読んでみようかなと思う人が増えると思う。
SFはおもしろい、読んでみて、ってハードルを下げると思うんだ。
むかしの作品は、それほど尖ったむつかしさがないから初心者にはいいよ。
追記:新しくなってた
とか思ってたら、もう新しい翻訳で出てた。
本屋で見てたはずなのに、頭に入ってない〜〜。
紹介だけしとくね。急いで読んでみるわ〜。


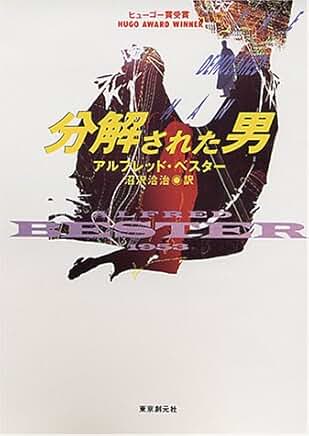
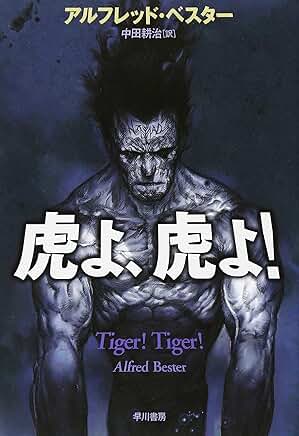
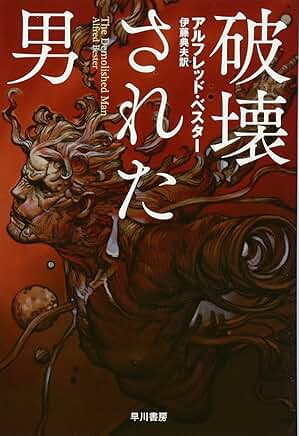











コメント