両性社会の人間関係の中で、あなたはたったひとりで生きていけるだろうか?
両性社会って、いま私たちが生きている社会と何がちがってくるのだろう?
あなたが女性なら、きっと両性社会の良さが理解できる。
そんな社会がここには描かれている。
【闇の左手】のあらすじ
忘れられていた植民星・ゲセンにも、宇宙連合から使節がやってきた。
たったひとりでゲセンとの外交関係構築のためにはたらくゲンリー・アイだが、両性社会の特異な人間関係のルールがなかなか理解できない。
彼の存在もまた、滞在するカルハイドの政府にじゅうぶんには理解されないまま、ゲンリーはいつのまにか政治的陰謀へと巻きこまれていった。
隣国へ逃れたゲンリーだったが、さらに事情のわからない陰謀のせいで捕らえられ更生施設送りとなる。
果たして、外交関係は構築されるのだろうか?
両性社会に住む人々は両性具有だが
両性っていうのは「男」と「女」。赤ちゃんが生まれたときに聞かれるアレ。
今でこそ「ジェンダー」「フェミニズム」「LGBT」などの言葉がメディア上に普通にふんだんにあらわれている。
が。
真剣に正確にそれらの言葉の意味を調べたり、考えたりしたことがある?
 さとう
さとうさとうはイメージ先行で興味本位でした。正確なことはわかってなかった。当事者の方々、ごめんね
この本は「両性社会」って言葉がキャッチーで、またヒューゴー賞とネヴュラ賞のダブル受賞だったので、けっこう知られている。
だからいろんなイメージと期待を持って手に取ったひとが多い(だろうな)
読みはじめると、文体や小説の構成などで「とっつきにくいわー」と思ったひとも多いだろう。
小説としてはおもしろくてよいデキ。
だが、主人公ゲンリー・アイの物語風任務報告とゲセンの昔話や伝説が交互につづられている形で進んでいくので……



こういうところが「SF、ムズイから苦手」とかって思われちゃうポイントのひとつよ
でも読み続けていると、昔話や伝説のナニカがじわじわ〜っとしみこんでくるみたいな感じを受ける。
そして実は、「両性である」ことよりも植民星の「独自の文化や社会を理解する」ことの方が大事で大変なのだということがテーマなんではないの?とわかってくる。
両性であることは単にひとつのファクターでしかない。
いやはや、いつの世も何の話も結局はそこに引っかかってくる。
異文化を理解するのは苦労するよね。
でも、異ではなくても相手をちゃんと理解するのはむつかしい。
両性具有をイメージすると
両性具有ってことはひらたく言うと男でもあり女でもあるってこと。
雌雄同体っていう言いかたなら学術の分野でむかしからある。
植物や昆虫、カタツムリやミミズなんかはむかしから知られているね。魚にも、最初はオスだけど成長過程やある条件下でメスに性転換するものもいる。


創作や表現の世界では人間でも両性具有がたくさん登場する。
けれど、実は現実世界でも「男」とか「女」にわけられない、もしくはわけられたくない多様な性の形が存在している。
古くは「半陰陽」「インターセックス」とか呼ばれ今風なら「Xジェンダー」っていうところ。
が。
このテーマはふくむものが多すぎて、正しく理解するのがむつかしい。
むかしは医学的に「性分化疾患」というとらえられ方をしていた。
けれど、実像とちがう偏見にさらされて苦しんでいる人もいる。
そもそも、病気じゃないでしょ?



だから現実社会では下世話なイメージを持たないでほしいとさとうは考えています
ただ、フィクションの世界では、ストーリーをどんなふうにでもつくっていける、貴重な人材ではあるんだよねぇ………
子孫を残すための性と生
「性」はなぜ、ひとつではないのだろう?
それは生きのこり生きつづけるため。
種の多様性を維持するためね。
多様性を維持するために、数え切れない組みあわせを生みだすシステムとして複数の「性」が必要なの。
「両性社会」に暮らしているのは「両性具有」の人間で、種としては「両性具有種」というひとつの種しかいない。
でも、生まれくる子孫はそれぞれの父親 × 母親の子どもたちで、多様な遺伝子の発現の結果となる。種としての滅亡を防ぐことができる。
ゲセン人は両性具有種なので、ある子どもの父親が別の子どもの母親となることもある。
それがゲセンという世界。
そんなシステムになってしまったのは、ゲセンがとても厳しい自然環境をかかえる植民星だったから。子孫を残すためにヒトは生き物として適応していく。
ま、もちろん、そんな厳しい星で植民していくために遺伝子的な改変も加えているけどね。
未来世界を創造する快感
この本は、未来史というカテゴリーに入る話だ。
アーシュラ・K・ル・グィンの作品の中でも「ハイニッシュ・サークル」と呼ばれるシリーズのひとつ。
ハイニッシュ・サークル(またはハイニッシュ・ユニバース)とは、超高度な科学文明を持つ古代ハイン人がはるかな過去にさまざまな惑星に植民地(星)をもうけ、膨大な時間の流れの中で失われたそれらを再び見いだして宇宙連合をつくった、という設定。
ル・グィン独自の架空の宇宙世界での未来史の話。



宇宙で、未来の話は、SFでは王道かな
SF作家が小説を書くときに、ひとつの小説では自分の考えるものを全部は語りつくせない場合、いくつもの話を展開するきっちりした土台をつくる。
それが「◯◯世界」と呼ばれるその作家独自の架空の宇宙世界、架空の歴史になる。
「未来史」の「史」とつけるかどうかは別として、SFはかなりの部分、自分の考えた未来世界や宇宙世界の話だ。
科学に基づいている(と想像する部分もふくめて)まるで “神”にでもなったかのような気持ちで世界をつくっていける。



あまりにご都合主義な、自分勝手な設定や話ではファンに支持されにくいけど
この、世界を創造していけるという部分こそが「今」「ここ」のフィクションとはちがう。
可能性に希望をたくし、未来に向くことの快感を楽しめるジャンルだとさとうは思ってる。
世界を創造し解決策を探っていけるというのは快感につながる。
しかも脳内で自由に楽しめる。
さとうがこの本を読んだ理由
本を買うか買わないかを考えるときに、いつも裏表紙や目次などをていねいに見る。
そこに「両性社会の人間」っていう記述があったから、もう無条件に買いだった。
なぜならさとうは、男女の社会的な差についていつも憤慨していたクチだから。
両性社会ならば、みんなが等しく義務も権利も手にするわけじゃない?
これは読まないわけにはいかない。



特に女性は共感するところがある、と思うわ
いわゆる「エロ」ではない「性」について考えながら、ゲンリーは異文化社会と苦労のうえゲセン人と理解しあっていく。
なぜならゲセン人からすれば、ゲンリー・アイとその所属している世界もまた異文化社会だから。
理解は相互の努力による。それがやがて外交関係構築へと結びつく。



「わかってよ〜」はお互いさま〜
それがわかるだけでも、この本を読んだ意味がある。


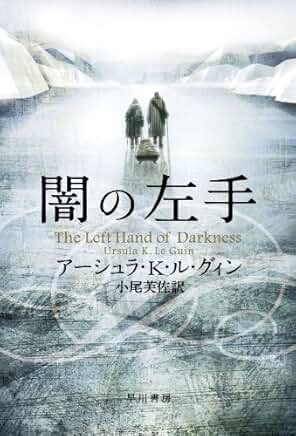











コメント